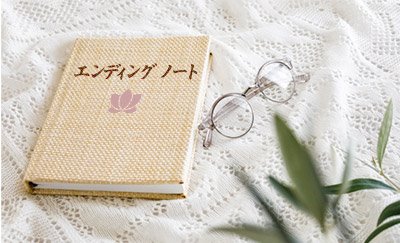いわゆる「終活」というワードが広まりつつある昨今ですが、専門家の一人としては、「遺言書」を残しておくという行為はまだまだ一般的とはいえないのではないか、と感じています。
遺言書といえば、お金持ちの資産家にしか関係がないのでは?と思われるかもしれません。しかし、一般的な普通のご家庭であっても、「遺言書が残されていれば相続でこんなにもめなかっただろうに」と思う事案を数多く見てきました。
そこで今回は、遺言書を残すことを一般的にしたい!という思いを込めて、「遺言書の書き方」についての解説をしていきます。
無料で6,000以上の
テンプレートをDLするなら!
>会員の方はこちらからログイン
遺言書作成のすすめ
遺言書は、自身が築いてきた財産を、相続人となる家族だけでなく家族以外にも遺すことができる、法的に有効な意思表示になります。
もし遺言書を残していなかったら、それがさほど大きな資産でなくても、相続財産をめぐって大切な家族が争う事態に発展してしまうかもしれません。
誰もそんな悲しい事態は望んでいませんよね。
遺言書は、法的効力を持たせたい内容だけでなく、自身の思いを形として遺すことができる手段にもなります。
自身が望む家族等の未来のためにも、亡くなった後のことを考えて遺言書を作ってみてはいかがでしょうか。
法的に効力のある遺言書を遺すには?
遺言書を法的に有効なものとするには、法律に則った形式で作成しなければなりません。
遺言書の主な作成方法として、全文を自筆する「自筆証書遺言」、公証人が作成する「公正証書遺言」があります。
公証役場にて「公正証書遺言」を作成する場合は、法的に有効な遺言書を公証人がしっかりと担保した形で作成してくれますが、「自筆証書遺言」の場合は注意が必要です。
決して難しい話ではないのですが、遺言書としての形式的なルールがあるということをはじめに理解しておきましょう。
「遺言書の書き方」については、後述します。
遺言書で残せる法的に効力のある内容について
実は、遺言書で残すことができる法的に効力のある内容は、法律(民法)で定められています。
遺言書にて残せる法的効力のある内容は、主に下記の事項になります。
「推定相続人の廃除およびその取り消し」について
推定相続人というのは、法的に相続人になる予定の地位にある人ですが、その推定相続人から相続人の地位を無くしてしまうのが、「相続人の廃除」という行為です。遺言者が生前に、相続人から「虐待や、重大な侮辱を受ける」などの事情があった場合に、その相続人から相続権をはく奪することができます。
それを、遺言書でおこなうことが可能です。
なお、遺言書にてそれを実行する場合には、遺言執行者が必要になります。
「相続分の指定および指定の委託」について
遺言によって、法定相続分の割合とは異なる「相続分の割合を指定」することや、「指定の委託」をすることが可能です。
「相続分の指定」は「法定相続分」よりも優先されるので、自分の希望した相続人に多く財産を残したいときには、その実現のために、遺言にて「相続分の指定」をしておく必要があります。
「遺贈」について
自身の死後に、財産を相続人以外の第三者に譲り渡したい場合には、生前に「死因贈与契約」を結んでおくか、「遺言書による遺贈」をすることにより可能となります。
「遺贈」には、「財産の○分の○」といった財産の割合を指定する「包括遺贈」と、「○○の土地」や「預貯金○○円」といった特定の財産を指定する「特定遺贈」があります。
「包括遺贈」の場合は財産の割合だけが指定されているので、包括受遺者は指定された割合に従ってどの財産を承継するか「遺産分割協議」をしなければなりません。
遺言者の死亡後に相続人や受遺者の間で協議が必要になる「包括遺贈」を選択する場合は、その点を留意する必要があります。
「遺産分割方法の指定および指定の委託、遺産分割の禁止」について
遺言書に残すことによって、「遺産分割方法の指定」や「指定の委託」が可能です。
遺産分割の方法には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」があります。
どのように遺産分割をするか、遺言書にて指定することが可能になります。
また、「遺産分割の禁止」を指定することも可能です。
ただし、「遺産分割を禁止」する場合、禁止できるのは相続開始の時から5年以内です。
「配偶者居住権の設定」について
令和2年の民法改正により、配偶者居住権が認められるようになり、遺言によって配偶者に居住権を取得させることも可能となりました。
これには、相続開始時に下記の3点の要件を満たしていることが必要です。
- 遺言者が対象建物を所有していること
- 配偶者以外の者と対象建物を共有していないこと
- 配偶者が対象建物に居住していること
「相続人相互の担保責任の指定」について
遺言の内容として、「相続人相互の担保責任」について免除や減免等の指定をすることが可能です。
「相続人相互の担保責任」とは、相続財産に問題が見つかった場合に、問題のあった相続財産の損失分を相続人間にて公平になるよう担保責任として負担し合うことです。
その問題ある相続財産を承継した相続人に対し他の相続人が負担すべき分を損害賠償として支払う義務を、遺言書にて免除する等の指定が可能となります。
「特別受益に関する免除」について
相続人が遺言者から生前に贈与や遺贈によって受けた特別な利益を「特別受益」といいます。
相続人の中に特別受益を受けた者がいた場合、相続発生時の財産にこの特別受益の財産分を持ち戻した財産の合計を相続財産の全体の価額としなければ、法定相続分を侵害することにもなり、相続人間にて不平不満が発生してしまいます。
法律的には特別受益分は持ち戻して相続財産を計算するのが原則ですが、この「持戻し」を遺言者が望まないのであれば、「遺言にて特別受益の持戻しの免除」をすることが可能です。
「財産の寄付」について
最近普及しつつある「遺贈寄付」とは、「遺贈」によって自身の遺産を寄付することです。
遺贈寄付をする際に注意すべき事項として、寄付をしたいと思って「遺言書」に「遺贈寄付」の内容を残していても、寄付を受けた側が拒否をするケースも想定されます。事前に寄付したい先に話を通しておくことも必要でしょう。
特に、「包括遺贈」をしてしまうと、負債を負うリスクもあるため、寄付先もそれを懸念して拒否をする可能性が高まります。
「遺贈寄付」を検討される場合は、そういった点も考慮しておきましょう。
「信託の指定」について
信託をするにあたって必要となる事項を遺言書に記載することによって、「信託を設定する」ことも可能です。
信託とは、自分の財産を信頼できる人(受託者)に預けて管理してもらい、その財産を家族など特定の人(受益者)のために使ってもらうしくみです。たとえば、信託銀行を受託者とし、貯金を「○年間孫の学費として息子(娘)に渡してほしい」といった信託も可能です。
遺言によって信託をする場合、信託契約と違って一方的に内容を決めて書き残すことができます。つまり、受託者の事前の同意なく遺言に残すことが可能です。
しかしながら、受託者にも都合がありますから、遺言による信託を拒否することもできます。
そのため、事前の同意は必要ないとしても、受託者から事前に了承を得ておいたほうがよいでしょう。
「一般財団法人設立のための財産の拠出」について
遺言者が、相続財産を財団法人設立のための財産として拠出したいと考える場合には、遺言書にて自身の死後に「一般財団法人」を設立することが可能です。
具体的には、遺言書に設立したい一般財団法人の「定款内容」を記載し、その実現のために遺言執行者を指定し、設立手続きは遺言執行者において実行される流れとなります。
「保険金の受取人の変更」について
保険金の受取人の変更も、遺言書にて指定することが可能です。
本来ならば契約の変更手続きになるのですが、平成22年の保険法の改正によって、遺言での変更が可能となりました。
ただし、遺言にて受取人の変更が指定されていても、「保険会社への通知」が必要となることには変わりはありません。
この通知が遅れてしまったり、遅れなくても通知する前に保険金が「元の受取人」に支払われてしまったりするケースは十分に想定されます。
特段の事情がなければ、生前の内に受取人の変更をしておくことに越したことはないでしょう。
「祭祀承継者の指定」について
先祖のお墓を守って供養する「祭祀承継者」を遺言にて指定することが可能です。
「祭祀承継者」は「祭祀財産」を承継することになります。
「祭祀財産」とは、仏壇等の祭具や墳墓、家系図等の系譜のことをいいます。
「祭祀財産」は、被相続人の指定による承継が優先されますので、指定が無ければ、慣習や家庭裁判所の指定により承継されることになります。
ちなみに、「祭祀財産」は相続財産には含まれないので、本来は遺産分割の対象とはなりません。
「認知の指定」について
結婚していない相手との間にできた子供は、「認知」しなければ法的には親子関係にならず、その子供には相続権は発生しません。
生前に認知していなかった子に対して、遺言書にて「認知」することが可能です。
「認知」をすれば、その子も相続人となり、他の相続人と変わらず法定相続分を得る権利が発生します。
「未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定」について
もし、遺言者に未成年の子がいて、その子の親権者が遺言者だけであった場合は、当然ですがその未成年者である子の親権者がいなくなってしまいます。
そのようなケースでは、遺言書にて未成年後見人を指定することができます。
遺言書にて未成年後見人を指定した場合には、未成年後見監督人も合わせて指定しておくとよいでしょう。
未成年後見人は、未成年者が成人するまでの期間、財産の管理やその子の監護・教育に関しても重大な責任を負う立場になるので、大切なお子さんのために信頼できる方を指定しましょう。
「遺言執行者の指定および指定の委託」について
遺言書の内容を実行するためには、相続人全員で協力しておこなうことも可能ですが、手続き上難しいケースが発生し、結果として遺言書の内容の実現がスムーズに進まないといった事案が発生します。
そうならないためにも、遺言書を残す場合は「遺言執行者」を定めておいた方が、遺言の内容をスムーズに実行できます。
遺言執行者は、遺言内容を実現するための手続きを実行する権限を持ちます。
そして、遺言執行者が定められた場合、相続人は勝手に相続財産の処分行為をできなくなります。
遺言書の内容を確実に実行するためには、「遺言執行者の指定」または「指定の委託」をしておくことをおすすめいたします。
「著作物の実名登録の申請をなすべき者の指定」について
マイナーな内容かも知れませんが、「著作物の実名登録の申請をなすべき者の指定」を遺言でおこなうことも可能です。
これは、生前は著作物に対して匿名にしておきたいが、死後は「実名の登録により得られる著作権保護期間の延長等のメリット」を享受するために、遺言にて「実名の登録」をおこなう場合などに活用されます。
遺言書の書き方について
冒頭でも述べたとおり、「公正証書遺言」であれば公証人が公正証書として作成してくれるので心配いりませんが、「自筆証書遺言」として遺言書を作成する場合には、法的に効力が認められるようにルールに則って作成する必要があります。
そこで、以下ルール通りに作成されているかどうかを確認するためのチェック項目を記載しておきます。
- 全文が自筆(パソコン等ではなく自身の手書き)にて書かれている (相続財産目録は、手書きでなくてもOKです)。
- 遺言書の「作成年月日」が自筆で記載されている。
- 遺言者の「氏名」が自筆で書かれていて、押印がある。
- 記載内容の訂正がある場合、所定の方式に則って訂正されている (訂正方法は多少煩雑なので、全文書き直しをおすすめします)。
詳しい書き方については、解説付きの遺言書サンプルがダウンロードできますので、参考にしてください。
遺言書・遺産分割協議書のテンプレート紹介
本遺言書雛形は、別紙として作成する財産目録をもとに、それぞれ相続人を指定する形式になっています(本書ではすべて配偶者としていますが適宜書き換えてください)。
遺言執行者と、遺言執行者への報酬についても記載しています。
なお、本書は自筆証書遺言を作成する際の参考案です。解説を参考に、遺言者が自筆にて作成し、捺印してください。
※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。
※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。
本遺言書は、全財産を包括的に指定する相続人(本書では配偶者)に相続させ、指定した相続人が死亡した場合の「予備的遺言」を含んだ内容になっています。
必要に応じて遺言者執行者や、遺言作成に至る経緯を記載してください。
なお、本書は自筆証書遺言を作成する際の参考案です。解説を参考に、遺言者が自筆にて作成し、捺印してください。
※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。
※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。
遺言書の種類および保管方法について
遺言書の種類は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。
「自筆証書遺言」について
「自筆証書遺言」は、遺言書をすべて自筆で残した遺言書です。
法的なルール則って作成すれば、いつでも作成できるしお金もかかりません、最も手軽に残せる遺言書になります。
「遺言書は本人が保管する」必要がありますが、法務局による「遺言書保管制度」ができましたので、最近では、安価で遺言書を保管できる「遺言書保管制度」を活用するケースが増え始めています。
「公正証書遺言」について
「公正証書遺言」は、公証人への手数料が発生するため、手続き費用としては負担が大きくなりますが、法的にも有効な遺言書を残したい場合には、最も安全・安心な方法です。
「公正証書遺言」は公証役場においても保管されデータベース化されるので、全国どこの公証役場においても検索を申し出れば、作成した遺言書の存在を確認することが可能です。
また、作成後には公正証書遺言の原本と同じ内容の正本・謄本を渡してもらえるので、自身で正本・謄本を保管しておくこともできます。
「秘密証書遺言」について
最後に、聞き慣れないかもしれませんが「秘密証書遺言」について解説します。
「秘密証書遺言」とは、公証人と証人2人以上に遺言書が存在することを証明してもらいながら、本人以外が遺言書の内容を見ることができない状態で封をして残す遺言書になります。
遺言内容を誰にも知られたくない、秘密にしたい場合の遺言書形式ですが、あまり用いられることがないのが実情です。
「秘密証書遺言」は公証役場にて手続きを取りますが、公証役場には「遺言書を作成したという記録だけが残る」ので、「遺言書自体は本人が保管する」必要があります。
まとめ
遺言は、自身の財産を誰に対してどのように残しておきたいかを、ご自身の意思のみで決められる唯一の方法です。
今回のコラムでは、法律で定められた効力のある遺言事項についての内容を中心に解説しましたが、もちろん、法的な拘束力はなくても遺言として伝えたいことや希望する内容を盛り込んで作成することが可能です。
遺言書の「付言事項」として、なぜこのような遺言内容にしたのか、その思いや経緯を遺しておくと、遺族等に対して自分の意思がより伝わりやくなると思います。
いずれにしても、遺言の重要な要素として、ご自身の意思で遺す必要があるということを考えると、元気なうちから遺言を作成しておく・毎年の恒例行事として1年に1回は遺言の内容を見直して作成し直す、というのがよいのではないでしょうか。
執筆者情報
エニィタイム行政書士事務所 代表 中村 充(行政書士)早稲田大学商学部卒業後大手通信会社に入社、法人営業や法務業務に携わる。2009年に行政書士資格を取得し、2017年、会社設立及び契約書作成に特化した事務所を開業。弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士等各種専門家との連携体制を構築し、企業活動のバックオフィス業務すべてのことをワンストップで対応できることも強み。
プロフィールを見る >行政書士KIC事務所 代表 岸 秀洋(行政書士・銀行融資診断士)司法書士事務所での勤務を経て、2006年に行政書士試験に合格、2014年に行政書士登録開業する。司法書士事務所勤務時代から約100件以上の会社設立サポートを経験してきたなかで、単なる手続き業務にとどまらない伴走者としてのサポートをしていきたいと考えるようになる。事業計画・損益計画の作成から融資のサポートや資金繰り計画など財務支援までおこなうのが強み。
プロフィールを見る >
遺言書や遺産分割協議書など、相続に関する書類のテンプレートです。
これらの書類を作成することで、後々の相続争いを防ぎ、不動産や金融機関での名義変更手続きなどもスムーズに進めることができます。
なお、遺言書は、自筆証書遺言を作成する際の参考案(例文)で、解説付きです。全文を遺言者が自筆で作成し、捺印が必要となります。
関連記事